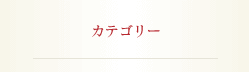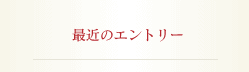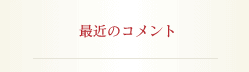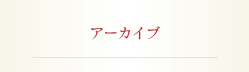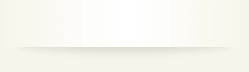| 「恋愛サバイバル」 | 2017年10月21日 |
柴門ふみさんのエッセイ「恋愛サバイバル」を読みました。
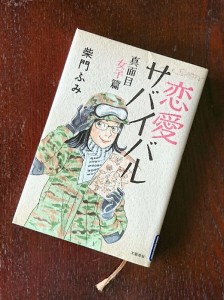
結婚生活にトキメキは不要です。
結婚は「生活」の場なので、
そんなところでときめいていては体が持ちません。
なんて、夢のないことをおっしゃるのでしょう柴門さん。。。
ときめく恋をして結婚
そして、甘~いスゥィートホームは
誰もが夢見ることではないでしょうか
と、読み進むと
夫婦は、互いに尊敬しあっていなくては長持ちしません。
どちらかが一方を軽んじて、
馬鹿にしているような関係は、いびつです。
尊び合う関係。
読んでいて、2013年組さんの
哲也さん&由佳ちゃんを思い出しました。
お二人は志しある農作がご縁でお付き合いが始まりました。
由佳ちゃんが結婚前に哲章さんのことを
「好きだけど、ときめいいたことがない。
一緒にいても、まったくときめかない」」って
金澤syugenで言っていましたっけ^^。
結婚式の日、由佳ちゃんのお父様とお会いして
ビックリ!
哲章さんはお父様にソックリなのです!
お父さん似の人に恋をするという法則は
本当なんだ!って思いました。
えー、現在のお二人は夢が叶って
オーガニック農業で蓮根作りをされています。
今年は二番目のお子様も誕生と幸せな
NEWSが続きます。
お互いを尊重しあって温かい家庭を
創るのが素敵なご夫妻のカタチですね。
哲章さん&由佳ちゃんの
白山比咩神社さん挙式&和田屋さんお食事会の
「真珠星祝言」Happy Reportです。
http://www.kanazawa-syugen.jp/happy/index.php?id=254&cat=cat2
2017年10月21日 カテゴリー: 気まま図書館 | コメントはまだありません »
コメントをどうぞ
| 「笹の舟で海をわたる」 | 2017年10月8日 |
角田光代さんのエッセイ明るくて好きなのですが
小説はけっこういつもディープです。
「笹の舟で海をわたる」も独特の闇がありました。
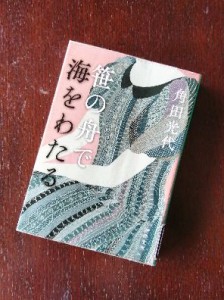
主人公の左織は、兄と姉がいて
末っ子だったから自分では何も決めれなく
いつも人の言うまま
起こったことは人のせいにする。
一方、友人の風美子は社交的で行動力あって
力強く存在感もある女性です。
疎開先で知り合った二人は
戦後、再会し義理の姉妹になるのですが
それは友人の風美子が仕組んだことだったのかもしれません。
風美子の夫が左織にポツンと話します。
「あいつに生かされているんじゃないか(略)
あいつの筋書きのなかで生きているような」
こういう経験はないけれど
そんな風に影響力があるというか
コントロールできる人っているような気がします。
さて、左織には子供が二人いてどちらも
実子なのだけど愛おしさが違うと感じています。
自覚があったからこそ、慎重に隠した。(略)
娘をかわいいと思えない、鬼のような自分を隠すことに必死だった。
角田さん自身が母親から愛情を
注がれなかったのかしらん
いやいや、小説にあることが
すべて実経験だなんて無粋でした。
そもそも疎開先で陰湿ないじめがあったことが
度々描かれるのですが67年生まれでは
戦争体験はあるわけないのです。
親の死をきっかけに遺産相続でもめ
兄弟仲がぎくしゃくしだして
付き合いが無くなるとかいった
女の一生にありそうな出来事といった
内容でもあって読む人が少しずつ共感できます。
この小説の中でとても印象に残った言葉は
今がしあわせなように見えても、そんなものは
すぐに日常の煩雑に紛れてしまう。
しあわせは点のようなものかもしれないと左織は考える。
線のようには続かない。
あらわれてはすぐに見えなくなる。
確かにそうですね。
友人の風美子と夫の関係をいぶかしみ
猜疑心を持つ左織、
ネタバレになってはいけないからかけないけれど
どうなるんだろうとドキドキでした。
笹の舟で海をわたるようなそんな危うさを
終始感じる一冊でした。
2017年10月8日 カテゴリー: 気まま図書館 | コメントはまだありません »
コメントをどうぞ
| 「本性」 | 2017年10月1日 |
読んだことない作家さんの作品を
読んでみようと図書館で選んだのが
黒木渚さんの「本性」です。
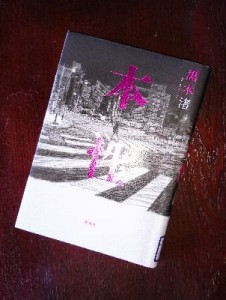
SM 、同性愛、介護、ネグレクト、風俗、
ギャンブル、DV、対物性愛(※)
と、扱っていることがディープなお話が三つ。
この中で「対物性愛」ってのは
「生命のあるものにではなく、
無機質な物に愛情を抱く性的倒錯、
嗜好の一種」とのことです。
情景がリアルに浮かんで
気持ち悪くなることもありましたが
登場人物がすべて違う世界の人だから
と、怖くはならなかったです。
二つ目のお話だけが主人公に
「自分だったら」とおきかえてみました。
女優になりたくて
演じることが好きで
いききと暮らしていた主人公が
屈辱と言えるほどの挫折感に苦しんでいた時
とてもいいタイミングで
プロポーズされ夢をあきらめ結婚します。
そして、日々の生活の中で
自分が諦めた夢のことを何度も思い返した。
という思いをいだきます。
「あのときああしていれば」
「もうひとつの道を選んでいたら」
人生はいくつもの分岐点があって
振り返る時、歩まなかった方の道を
選んでいたらとふと考えることがあります。
私にとって過去のすべての経験は
遠回りなんかじゃなかったんだって
今は思えます。
人との出会いに大変恵まれ
和婚プロデューサーとして
金沢の街並みを舞台にした「金澤和婚」
という文化を創りあげる夢を
叶えることができました。
良きお客様、素晴らしい技術を持つ方々、
金澤syugenとともにお仕事をしてくださる方々、
そして、家族との出会いがあったことに
あらためて感謝です☆”
2017年10月1日 カテゴリー: 気まま図書館 | コメントはまだありません »
コメントをどうぞ
| 「風葬」 | 2017年9月22日 |
桜木紫乃さんの暗く重たい世界と
情景描写の美しさに今回も引き込まれました。
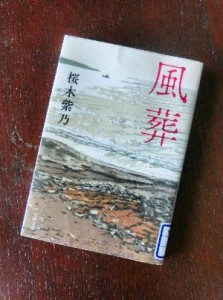
「風葬」は北海道の涙香岬(るいかみさき)が
物語のキーワードになります。
北海道の海岸線町では、
拿捕・密漁・密輸・マフィア・
二百浬領土問題・抑留・裏社会・
諜報活動と昭和の米ソ冷戦の頃は
そんなおどろおどろしいことを
身近に感じていたのかしら・・・・・。
物語は幾組もの親子が交差します。
出生の秘密を明らかにしようとする
女性と、認知症の母。
ソ連船に拿捕され殺された父親と女子生徒。
その時、担任だった父親とともに
事件を解き明かそうとする息子。
その息子が担任の時に子供を
失ったと訴訟をおこす父親。
学校側の弁護をする弁護士の父親と娘。
根室の古い旅館の裏社会に暗躍する女将と
ソ連に情報を流す息子。
親子達が他の親子達と繋がってゆき
ミステリアスな物語はさらにさらに
幾重にも絡まってゆきます。
そして、自殺・北海道に逃げて来た男女、
生まれるはずではなかった子ども、
ネグレクトといったことが陰湿にからんできます。
遊郭がありかって栄えたことを
うかがい知れる町はひっそりとさびれ
丁寧な描写に漁師町の生臭さや
鉛色の空、湿度までも感じ物悲しさが募ります。
終盤は絡みついていたモワっとした霧が
徐々に晴れていくような清々しさがありました。
2017年9月22日 カテゴリー: 気まま図書館 | コメントはまだありません »
コメントをどうぞ
| 「博士の愛した数式」 | 2017年9月18日 |
トーク番組に芥川賞作家の小川洋子さんが
ご出演でお話されていることが
すごくおもろくて興味を持ち
「博士の愛した数式」を買ってきました。
(なるべくモノを増やさない生活を
していますが、文庫本は買っていいことにしています^^)
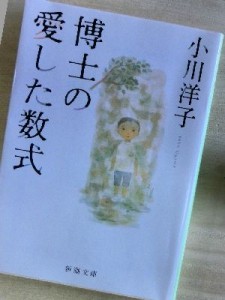
数字と人を紡いでゆく物語です。
事故の後遺症で「もてる記憶が80分まで」
という数学の教授が美しい所作で
数式や数字の世界の美しさを教えてくれます。
懐深く温かい博士(教授)を慕う
思いやりと好奇心を持つルートは
家政婦の子供です。
「老人と子供の友情」って
いうとこが無条件に好きです。
映画「ニュー・シネマ・パラダイス」でも
「老人と子供の友情」に感動しました。
物語の終わりに近づくと鎖骨の奥あたりが
ザワザッワとして涙が溢れでました。
ラストが大好きで、すごい勢いで
鎖骨の奥がキューンキュンしました。
登場人物の優しさにあふれているお話でした。
私は数字ってものが苦手。
たかが、レシートとかも見返すの
好きじゃないのですが
この小説は数字のロマンを感じました。
小川洋子さんすごい人です。
2017年9月18日 カテゴリー: 気まま図書館 | コメントはまだありません »
コメントをどうぞ
| 「成功者K」 | 2017年9月14日 |
羽田圭介さんの「成功者K」は
なんかすっきりしない
が、読了後の感想でした。
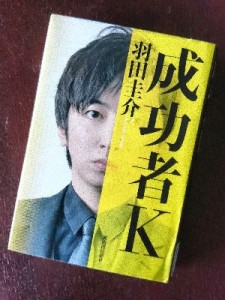
芥川賞受賞の「スクラップ・アンド・ビルド」が
軽快に読めたので期待し読み始めました。
今から読む人にネタバレになってはいけないから
「何が」かはかけないけど、とにかく
「あれ?こういう終わり方???」って感じでした。
週刊文春によるスクープや、
村田沙耶香さんの芥川賞受賞なども
登場してリアル感があります。
おもしろかったのは「週刊文春には
小説家枠があって、小説家のスキャンダルは
すっぱ抜かれない。」という話。
主人公Kが芥川賞を受賞してから
バラエティ番組にバンバン
出演しているのも自伝っぽく
フィクションなのか
ノンフィクションなのか
わからなくなるのだけれど
私生活を見ている感じです。
あと、成功者Kは性交者Kで
直接的な性描写が多いけれど
エロティシズム感は皆無で
トリセツ的な感じです。
さらに、主として展開する物語の中に、
もう一つの物語が展開する
「パラレルワールド」というカテゴリーで
(「入れ子構造」ともいうそうです)
ますます現実と虚構の区別がしにくくなります。
実話かしら?
いや、全部嘘?
まあ、小説がどこまでが本当の作者の
経験なのかなんて考えるのは野暮なことですか。
2017年9月14日 カテゴリー: 気まま図書館 | コメントはまだありません »
コメントをどうぞ
| 「パーマネント神喜劇」 | 2017年9月10日 |
万城目学さんの「パーマネント神喜劇」は
芋洗坂係長風の縁結びの神様が主役のフアンタジーです。
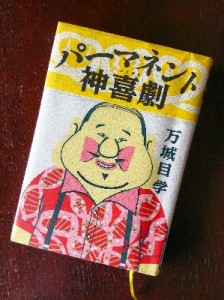
この神様が、やたら人間くさいのだけど
古来からの神話の中の神様も確かに人間っぽかったですね。
おもしろいと思ったのは
テストで間違った答えに×をつけるのは
間違いを否定しているわけじゃなく
封印しているのだそう。
で、×は雷からきていて稲光を模したものと。
夏の終わり、雷が鳴る頃に
稲穂が実るのを見て、雷が稲の先に実を
つけてゆくと考えられ「神鳴り」と呼ばれたそうです。
雷が稲に実をつけていく
なんと日本人の美意識は繊細で美しいことでしょう。
で、×は神鳴り(雷)の力で悪い物を封じようと
することなのだそうです。
言魂ってきっとあるんだろうなとも思っていて。
私の場合、同じ言葉を二度繰り返して、
それを言霊に変えて外の世界に送り出すのが仕事だからね。
この作業が楽しいのです。
「慎重すぎるサラリーマンが
前向きな人格へと成長」や
「ギャンブラーで当たり屋の男が
改心しまっとうになる」など
縁結びの神様が男女の思いを紡いでゆきます。
震災あとの地で“ドングリの実”が
縁あって繋がってゆくというお話では
こいうことあるって思いました。
偶然が重なってゆき
「あ、これ必然だったんだ」という感じです。
神様が人に与えるのはあくまでも
小さなきっかけで、それを感じうけとるは
人なんだ、と教えれます。
ホロリくるシーンもあって
神様はこうこなくっちゃね!
ハートゥォーミングな物語でした。
仕事柄、神社さんにはよくうかがいます。
今度から、ご神木や笠木の影も
興味を持って眺めたいとも思いました。
2017年9月10日 カテゴリー: 気まま図書館 | コメントはまだありません »
コメントをどうぞ
| 「女子的生活」 | 2017年9月5日 |
坂木司さんの「女子的生活」は
表紙がコミックっぽいのです。
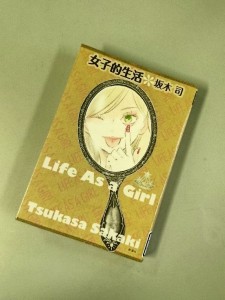
給湯室でのOLの会話や合コンの武勇伝、
女性社会のマウンティングや
バトルシーンと言った内容が続くと
もう読むのやめようかしらんと考えたりも。
主人公の幹生はブラック企業に勤める
トランスジェンダー(女子より女子力高い)で
時には奇異の目で見られます。
物事への洞察力がとにかく鋭い主人公。
瞬時に思考がめぐるFBIかKGBのような
心理分析に笑えました。
友人との「可愛さと毒気の入り混じり」の
“回転良い系”や”意識高い系”の会話も軽快です。
セクシャルマイノリティの主人公が
家族にカミングアウトした時の
両親のセリフに泣けました。
父親が
「本当に苦労したのは幹生だろう」
「子供の幸福を望まない親などいない」。
あと、同級生の後藤との友情はナイスでした。
作品の中でとても好きだった言葉は
「田舎者ってさ、場所のことじゃないよね。
ださい心を持っているっやつのことを、言うんだよ」
おおいに同感です。
あとがきで作者が「好きな人たちだったから、
書いている間、ずっと楽しかったです。」と
語っています。
物語の中の登場人物達に愛情を
注いでいる感じが十分に伝わってきて温かくなれました。
ペンネームは、自身の作品の登場人物の名前から
つけたそうです。
さて、作者の坂木さんは性別非公表
なのだそうですが「魂は女性」と感じました。
戸籍は男性のような気がします。
2017年9月5日 カテゴリー: 気まま図書館 | コメントはまだありません »
コメントをどうぞ
| 「ブルース」 | 2017年8月29日 |
9月の三連休「金沢JAZZSTREET 2017」を
案内する”ひがし茶屋街で芸妓さんが
サックスを吹くポスター”がカッコイイ( •ॢ◡-ॢ)-♡
石川四高記念館や金沢駅、音楽堂
武蔵、片町、市役所前などで開催され
中には無料のイベントも数々あって
軽快なジャズが金沢の街にあふれるようです。
さて、桜木紫乃さんの
「ブルース」を読みました。
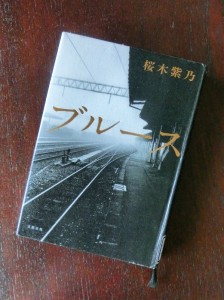
身体に傷を持ち、貧しく過酷な環境で
あらゆる差別を受けて育った男が
端正な顔立ちと妖しい色気で
出逢う女性達を魅了してゆき成功をつかみます。
かかわる個性的な女性たちもどこか可愛く
なにより男を深く愛しているのです。
独立した章ごとにそれぞれの女性目線で
描かれる短編小説が一人の男を
通して繋がっていきます。
こういうの好きです。
男がなにを考えていたのか
男が本当に愛した女性はいたのかは
読了後もわからずでした。
ただ、男には”深い情”があると感じました。
桜木紫乃さんの物語は暗い闇があって
ささくれだっています。
今回も、歓楽街が舞台になっていて
人身売買、裏社会、さらなる湿度を感じ
その世界観にひきこまれます。
人種差別や貧困に苦しんだ苦悩や絶望感を
表現した黒人音楽ブルース
このタイトルがぴったりの
艶っぽい小説でした。
2017年8月29日 カテゴリー: 気まま図書館 | コメントはまだありません »
コメントをどうぞ
| 「結婚の嘘」 | 2017年8月23日 |
「東京ラブストーリー」の原作者の
柴門ふみさんのエッセイ「結婚の嘘」を読みました。
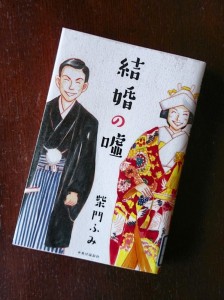
最初は旦那さまの弘兼憲史さんの
悪口の羅列で
「そんな一方的に言わなくても」と感じたり
退屈になりかけたりだったのだけど
読み進むとなるほどと感じることも。
【縁とは「相性」のこと】という章では
自分の意思で一緒にいるのだということ、
そして縁があるのだと認めることが、
心に折りあいをつけ、
「これでよかったのだ」と思う
気持ちに通じているのではないでしょうか。
最終章では、結婚することで
好きな人と一緒にいられることが
叶ったのだから他の欲を手放し
見返りを期待しないことをすすめられます。
印象に残っているのは
人は性的に惹きつけられる人にしか「恋」はしない。
性欲がなくなると、興味の対象は男でなくても、
犬でもガーデニングでもいいやということになるのです。
似たようなことを友人が
その昔、言っていましたっけ。
「男も女も、性的魅力がないと求めて
またその人に会おうとは思わない」と。
彼女は若い頃から、各分野に
哲学を持っていてふむふむと
納得したものでした。
色っぽいと感じるのは「相性」もありますよね。
最高に言いえて妙だったのはこれ!
これから浮気しようとしている夫が
目の前にいるとして、
「今、行ったら最後ですから」と
伝えることは正しいことですが、
過去の浮気に関して蒸し返し、
四の五の言うことには何の意味もありません。
夫婦や恋人間に限らずこれ、大事ですね
仕事や友人関係でも。
肝に銘じます(*^▽^*)!
「柴門(さいもん)」というペンネームは
サイモン&ガーファンクルがお好きで
付けたそうで、おしゃれなことです。
2017年8月23日 カテゴリー: 気まま図書館 | コメントはまだありません »