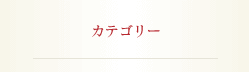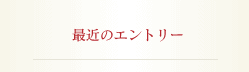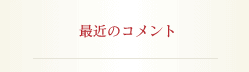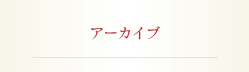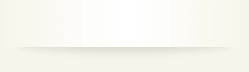| 「京洛の森のアリス Ⅱ 自分探しの羅針盤」 | 2018年12月10日 |
前作「京洛の森のアリス」では
ありすが天職を見つけるための
自分探しをするのですが
今作では蓮が自分探しの旅に行きます。
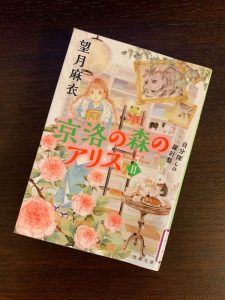
ありすは着物で書店の仕事をしています(*^▽^*)
と言うことで今回は表紙が和装です。
うさぎの棗が言います。
「一人一人、持っている速度が
違いますから、誰かと比べるのは、
そもそもが愚かなことなんですよ」
こんな風に深い言葉が数多くありました。
芸者さんの紅葉さんがありすに言います。
「『自分が感じたことを丁寧に教えること』と
『自分の意識を押し付けてしまうこと』は、紙一重や。
もし、自分の意識を相手に押し付けてしもたら、
同時に大きな『責任』も伴う。」
相手のためを思っての助言は
自分の考えを押し付けることではなく
愛情と覚悟を持ってしなければいけない
と言うことでしょうか。
また、「天職は一つとは限らない」と。
ありすは、本屋さんの店員さんに
なりたいと望みそれが叶って書店を開きました。
私も読んで面白かった本を人にすすめたり
誰かの好きな本の傾向を把握していたら
きっと、これ気に入ってくれるはずとすすめたり
あと、感想を聞くのも好きです。
私もウェディングプランナーが
天職って思っているけど
本屋さんもありなのかなぁなんてことも思いました。
2018年12月10日 カテゴリー: 気まま図書館 | コメントはまだありません »
コメントをどうぞ
| 「海の見える理髪店」 | 2018年12月5日 |
表題作「海の見える理髪店」は古い
邦画を見ているような懐かしさを感じました。
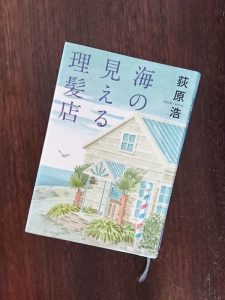
荻原浩さんのファンタジー小説は以前から大好きです。
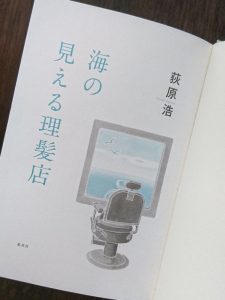
理髪店の店主は主人公の男性が
いつかきっと来ると待っていた気がします。
鏡越しに海に陽が落ちてゆく
様子が私のまぶたにもオレンジの
色み強く思い描けるようでした。
「いつか来た道」は娘の立場で
あったなら誰もが母親に持つ思いと
母親が老いてゆくことを受け止める
痛みが描かれていて切ないことでした。
列車に乗る時、幼い頃の辛い思い出と
憎しみに決別できたのだと感じました。
「遠くから来た手紙」は
ユーモラスでありながら
戦争中の夫婦の優しい情愛に泣けました。
他のお話も穏やかで心あたたまります。
この作品は直木賞受賞とあって
出版当時あまりにも図書館の貸し出し
順番が長く借りることをあきらめました。
この秋、気持ちがめいっていた時に
図書館をゆっくり歩いていて
本棚で目にとまったのでした。
本も人も出会うべき時に
出会えるものなんだと感じました。
2018年12月5日 カテゴリー: 気まま図書館 | コメントはまだありません »
コメントをどうぞ
| 「はつ恋」 | 2018年11月30日 |
村山由佳さんの「はつ恋」は
猫のユズちゃんとの生活
幼馴染の彼や親御さんのことなど
日常が綴られた自叙伝のような小説でした。
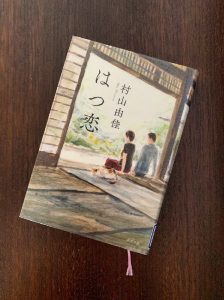
認知症の母親とのくだりではせつなくなって涙が出ます。
四季折々の自然を愛でる描写が繊細で素敵でした。
それら一つひとつが、まるで古い書物に
はさんでおいた栞のように、
ハナの記憶の一ページを開く手がかりになる。
虫の鳴き声や風のにおい、光の色で
懐かしいある情景が鮮やかに
蘇ることってありますよね。
毎年、繰り返される四季は
その都度に喜びと感動にあふれ
偉大なことです。
人生最後の恋は穏やかでありながら
ときめきもあって、胸の高鳴りは
はつ恋をした年頃から随分と
たっても変わらずにあるらしいです。
2018年11月30日 カテゴリー: 気まま図書館 | コメントはまだありません »
コメントをどうぞ
| 「水曜日の凱歌」 | 2018年11月26日 |
乃南アサさんの「水曜日の凱歌」は
716ページかなりショッキングな長編でした。
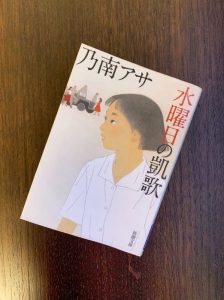
残酷シーンが多くプロローグで早くも
リタイアしようかってチラリと思ったけど
本章に入ると夢中で読み切りました。
これは映像化したら残虐過ぎて
直視できないだろうと思います。
想像できないようなむごたらしい
表現が続くのですが、涙が
あふれてとまらなくなったのは
学童疎開していた子供たちが
東京に帰ってきたら焼け野原で
家族がいなくなっていることに気づくくだりです。
誰も迎えに来てくれなくて独りぼっちで
どこに家があったのかもわからず
行くところもなく保護してくれる人もいない
食べ物もなく寝るところもない
心細いなんてもんじゃなかろう
その子たちは生きることができたんだろうか。
そして、命を奪われる瞬間に
きっと愛する我が子を思ったであろう
親の無念さはいかばかりか・・・・・。
今文字にしていても涙が出ます。
拗ねてばかりいた主人公の少女
鈴子が僅か一年で目覚ましい成長をします。
逞しく生きてゆく女性達が多く描かれており
その中でも鈴子の母親のしたたかさが
なんとも言えないのです。
鈴子の母親からみた戦前から戦後を
読んでみたいとも思いました。
一億総懺悔なんて冗談じゃない
ほとんどの国民が望んだ
戦争じゃなかったはずです。
弱者(ほとんどの国民)ばかりが
地獄(それ以上かもしれません)の
ような苦しみを味わされた戦争は
たったの75年前のことなのですね。
戦争を経験した人がご高齢となり
風化されていくことも考えられます。
こんな風に文字で戦争の惨さ愚かさ
人々の苦しみを伝える小説が
あっていいと思います。
どうか愚かしい戦争が二度と起こり
ませんようにと強く強く祈ります。
オススメの一冊です。
2018年11月26日 カテゴリー: 気まま図書館 | コメントはまだありません »
コメントをどうぞ
| 「緑の花と赤い芝生」 | 2018年11月19日 |
伊藤朱里さんの「緑の花と赤い芝生」は
真反対の性格の27歳同い年の
嫁と小姑が交互に語ります。
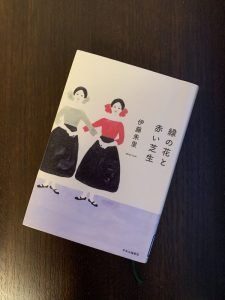
万人に嫌われたくない杏里と
他者とのかかわりが苦手な
エリートでリケジョな小姑の志穂子は
互いを嫌悪し怒り、けん制しあいます。
そして、二人は共に自身の母親を
受け入れられない息苦しさを抱いています。
語尾や語頭をひょこんと動かすそれには、小動物がしっぽを振る動きさながら場をやわらげる効果がある。
志穂子は関西弁で可愛く話す杏里を
このように見ていました。
確かに方言キュートだったり
親密さを深めやすかったりしますよね。
が、杏里と志穂子が対峙するシーンで
ゆわふるキャラなはずの杏里が
尼子インターの渚としか思えない
話し方となって(たぶん声のトーンも)
本音を互いにぶっつけあいます。
このシーン好きだったなぁ気分爽快( •ॢ◡-ॢ)-♡。
さて、お話にはおもしろい言い回しがいっぱいありました。
呼び鈴ってどうしてこんな音なんだろう? クイズに正解したときの音。ピンポーン。急にやってきておいて、自分が正しいと言わんばかりに。ピンポーン。これが正解です。ピンポーン。拒むあなたが悪い。ピンポーン。
あはは!言いえて妙
昭和歌謡が出てきたりけっこう笑えました。
随所に赤と緑の印象的な対比があります。
あ、今日「緑のおばさんの日」なんだそうです。
2018年11月19日 カテゴリー: 気まま図書館 | コメントはまだありません »
コメントをどうぞ
| 「「違うこと」をしないこと」 | 2018年11月12日 |
吉本ばななさんのエッセイ
「「違うこと」をしないこと」を読みました。
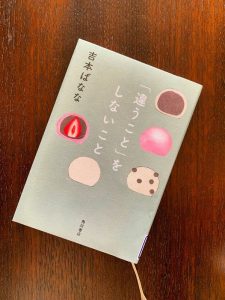
毎日は選択の連続で、自身の
心の声を聴くことこそ大切と
ばななさんは言います。
すごく好きな考え方は
時間は、未来から過去に向かって流れている
普段、時は過去から流れて
今に至っているって感覚ありますよね。
ですが、確かに創作祝言を
組み立てる時にこういう感じあります。
例えば「お二人の新生活には
ご家族の応援があったら
きっと心強い」と感じた時
親御様にむけてのさりげない演出を
提案させていただくことがあります。
もちろん、お二人の個性にあったかたちでです。
結婚式は、お二人がお互いのお家に
受け入れられる良い機会ですから。
良い結婚生活にむかって
お二人と一緒に思いの伝わる
結婚式を創り上げてゆきます。
あちこち気になったところから
読んでいたら、あとがきで
「パパブブレの飴のように、
どこから読んでも」とかいてありました。
大変、自由に読みました。
2018年11月12日 カテゴリー: 気まま図書館 | コメントはまだありません »
コメントをどうぞ
| 「ふたりぐらし」 | 2018年11月6日 |
桜木紫乃さんの新刊
「ふたりぐらし」は
夫と妻が交互に一人称となる
「ふたりで生きていくこと」を
テーマにした連作短編でした。
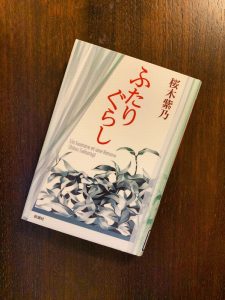
出会ったときからこの声が好きだった
と、妻が思う、その感じわかります^^。
声に、言葉や表情以上に
その人となりを感じます。
桜木さんの作品につき
闇世界や危なく艶っぽい男性が
登場する暗黒小説を期待して
おったのですがつまつまとした
毎日の暮らしの心の内が
丁寧に繊細に描かれています。
なんならそこにあるであろう
生活臭まで想像できました。
ヒモのような夫が
母親が亡くなって一年して
鳩サブレの缶に500円貯金と
遺されたメモを見つけます。
素っ気ない演技に騙されていたのか
親の心、子知らずに泣かされました。
夫の上司の男性が付き合っている
女性の母親を病室で看取る時に
整髪料のにおいを感じるシーンがあります。
「この匂いはお父さんのものだ」
と女性が言うのです。
のちに男性が語ります。
「お迎えっていうのは、
逝く側が心から望んだ人が来るのかもしれない」
このくだりがとても、とても好きでした。
来し方行く先を考える世代も
これから結婚を考える世代にも
良き一冊と思います。
本の帯に「一日一章ずつ」とあったけれど
こらえきれず一気読みしてしまいました。
2018年11月6日 カテゴリー: 気まま図書館 | コメントはまだありません »
コメントをどうぞ
| 「廓のおんな 金沢名妓一代記」 | 2018年10月23日 |
ずっと読みたかった井上雪さんの
「廓のおんな 金沢名妓一代記」を読みました。
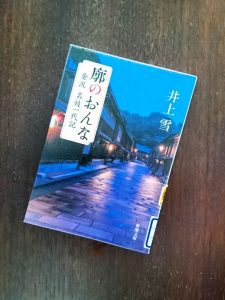
時代小説が好きで吉原や京都の
花街のお話には多く出会い
岩下尚史さんの随筆でも
新橋や深川、赤坂などなど
地域によって芸者さんの
営業の形態が違い
時代によっても役割が変わった
ことなども知り金沢の遊郭に
ついて書かれたものを探していました。
きぬさんも本が好きだったそうです。
「芸者は新聞や本を読んだら
恐ろしい人間になる。旦那さんが
つかなくなる」と禁じられ
読み書きを覚えることも嫌がられたため
泉鏡花を隠れて読んでいたと言うのです。
知恵がつくことを女将は嫌ったようです。
13歳の時にロシアの俘虜に
「オジョサン」と生涯に一度だけ
呼ばれてお嬢さんは良家の
子女をさす言葉だったから
胸が高鳴ったと言うのです。
そして、17歳で初めて横山邸で
お雛さんというものを見たと
書かれていてせつなくなりました。
明治から昭和までの世相
時代の移り変わりが描かれています。
金沢の町にロシア人の俘虜が
大勢いて(天徳院に300人も入れるんだ!)
随分と大切にされたようです。
金沢駅から出発する汽車を野町まで
見送りの人が連なっていたというのを
頭の中で想像しました。
元旦は日本髪を結い毘沙門さん
(宇多須神社さん)に黒留でお参り、
続いて挨拶まわりをしたそうです。
兼六園に屋形船が浮かび
霞ケ池を一周したなどなど
そんな時代があったんだと
セピア色の風景を思い浮かべながら
読み進めました。
母の世代というより祖母が使っていた
金沢弁の話し言葉で語られていて
それは、今の濁音が多い金沢弁ではなく
まあるい響きのある言葉で
今はまず聞くことのなくなった
「はしかい(賢い)」
「はごたえ(口ごたえ)」
などなど懐かしい方言に
タイムスリップした気分でした。
その昔の金沢の風習や暮らしなども
うかがい知れてオススメです。
2018年10月23日 カテゴリー: 気まま図書館 | コメントはまだありません »
コメントをどうぞ
| 「彼女の恐喝」 | 2018年10月15日 |
藤田宜永さんの「彼女の恐喝」は
昭和のドラマを観るような
どこか懐かしい感じがしました。
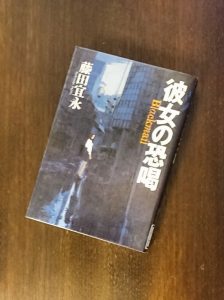
主人公の女子大生の矛盾している性質
「悪女だけど優しい」「狡猾だけど健気」
これは、作家さんの若い女性への
願望なのかしらんと想像しました。
主人公も含めて登場人物達が
暗黒の中にいながらも人としての情を
持ち続けていると感じられて心地よく読めました。
未読のページがもうわずかしかない頃には
いったいどう決着するのだろう
って、ハラハラ急いで読み進みました。
あまり、読まないラブノワールサスペンスですが
ドキドキおもしろかったです。
2018年10月15日 カテゴリー: 気まま図書館 | コメントはまだありません »
コメントをどうぞ
| 「静かに、ねぇ、静かに」 | 2018年10月9日 |
石川出身の作家の本谷有希子さんの
新作「静かに、ねぇ、静かに」は
ネット社会を描くホラー三作品でした。

一作目の「本当の旅」は
SNSで誰しもが持ったことのある
違和感が気持ちいいくらいに
あぶりだされています。
自分を探し続けたままアラフォーに
なった三人は一緒にいながら
SNSで会話をしたり、
加工、編集してインスタ映えする
写真を楽しい思い出として
SNSにのせ「作りものの旅」をします。
例えば「こんなもの日本じゃお金は払えない」と
感じている料理を懸命に写真を撮り
スマホの画面をのぞきこみ「おいしそう」
と、満足し冷えた料理を食べる
そんな三人は不気味です。
僕が本当はどう感じたかなんて、
たいしたことではないのだ。
画面の中の自分たちが
楽しそうで仲よさそうで
食べ物がおいしそうなことに
充足感を得るようになったというのです。
無神経でまわりへの迷惑おかまいなし
それでいてお気遣いな自分に酔っている感じや
ハラハラするようなポジティブ信仰
(思考ではなく)っぷりも違和感あります。
おもしろくってあっという間に読みおえました。
ネットショピング依存症の二作目
「奥さん、犬は大丈夫だよね?」
動画配信をする三作目
「でぶのハッピーバースデー」は
芥川賞の「異類婚姻譚」を
読んだ時のあの感じで
私にはうまく理解できませんでした。
2018年10月9日 カテゴリー: 気まま図書館 | コメントはまだありません »